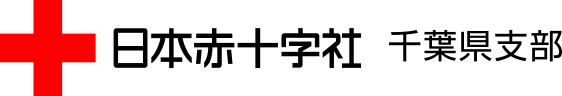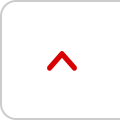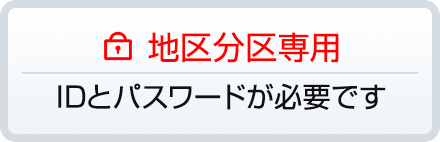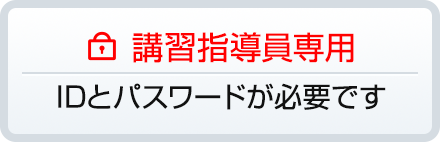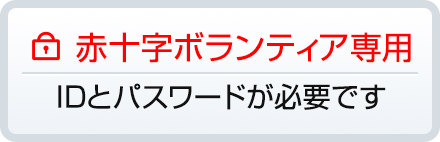赤十字は192の国と地域にあり、世界最大のネットワークを持つ人道支援組織です。その世界的なネットワークを活かし、日本赤十字社では世界中の災害や紛争、病気などに苦しむ人々を救うため、緊急時の救援や復興支援、開発協力など国際活動に取り組んでいます。
赤十字の国際活動
赤十字は、いかなる状況下であっても誰もが「自ら立ち上がる力(レジリエンス)」を持っていると考えています。その力が高ければ高いほど、自身の力でリスクを予見し、危機に対応し、回復し、さらに前進することが可能です。地域社会やそこに住む人々が危機にさらされた時、真っ先に対応するのは彼ら自身です。赤十字は、地域社会あるいは人々が持つ「レジリエンス」、とりわけ「地域の力(コミュニティ・レジリエンス)」を高めることを目指しています。
そのために、被災者への医療や衣食住の支援といった緊急救援だけでなく、その後の復興支援、そしてこの「レジリエンス」を培う長期的な開発協力という流れで包括的に取り組んでいます。
日本赤十字社の開発協力
日赤の開発協力事業は、「レジリエンス」の強化を目的として、世界で最も自然災害が発生しやすく被害が大きいアジア・大洋州地域と、気候変動の影響や貧困など、複合的な課題を抱えるアフリカ地域を重点地域とし、各国赤十字社とともに、「逆境に負けない地域づくり」を支援しています。
 学校での防災訓練(インドネシア)
学校での防災訓練(インドネシア)
 地域住民に肥料の作り方を指導するボランティア
地域住民に肥料の作り方を指導するボランティア
アジア・大洋州地域救急法普及支援事業
アジア・大洋州地域は、世界的に見ても自然災害の多発地域であるとともに、急速な発展による交通量の増加に伴い交通事故が深刻化しています。インフラや救急医療システムが発展途上であるこの地域では、災害や事故による傷病の予防に努めるとともに、けが人や急病人を救うために、市民による救急法の実践が重要となります。
今回は、救急法普及支援事業に参加するため、2月18日(土)から25日(土)までラオス赤十字社に派遣された当支部職員 柴崎総務課長に活動内容を聞きました。

総務課長(派遣当時)
ラオス人民民主共和国

- 面積:236,800㎢
※日本の本州とほぼ同じ - 人口:742.5万人 (2021年)
※埼玉県とほぼ同じ
交通事故が深刻化するラオス
ラオスはどんな国?
ラオスはメコン川が横断する東南アジアの国で、山岳地帯、フランス植民地時代の建築物、山岳民族の集落、仏教の僧院などで知られています。首都ビエンチャンには凱旋門「パトゥーサイ」や、食べ物・工芸品の店がひしめき合う朝市やナイトマーケットがあり、“世界で最も行きたい国”として知られています。
しかし、急速な経済成長に伴う自動車の普及や交通インフラの整備により、交通事故死者数が増加しており、首都ビエンチャンは同国において最も交通事故死が発生しやすい地域です。
 凱旋門「パトゥーサイ」
凱旋門「パトゥーサイ」
 朝の通勤ラッシュ(首都ビエンチャン市内)
朝の通勤ラッシュ(首都ビエンチャン市内)
ボランティアが救急車を運転
ラオスの医療水準は?
ラオスは、特に開発が遅れている後発開発途上国の1つであり、医療水準は近隣諸国と比べても極めて低い状況にあります。2015年時点の人口1,000人当たりの医師数は 0.272 人と、世界平均の1.804人を大きく下回っています。また、救急搬送(救急車)については、数少ないボランティア救急隊が運営しており、依頼してから到着まで非常に時間がかかるなど、地域住民が自分たちで応急手当を実施できるようにすることが非常に重要です。
救急法のノウハウを伝える
日本赤十字社の役割は?
ラオス赤十字社(以下、ラオス赤)は、そのために必要な救急法の知識・技術の普及を目指しているところですが、普及に必要な人材の育成や資機材の整備など自国だけのノウハウによる普及は困難な状況にあります。
そこで、日赤は、2019年10月からラオス赤が行う救急法普及事業に対して、人材育成や資機材整備のための財政支援、指導員の派遣による技術支援を行うこととしました。今回、渡航制限の緩和を受けて、支援開始後初めて、私を含めた日赤職員4名が現地を訪問しました。
現地での活動内容は?
1日目は、救急車による患者搬送を行なっているボランティア救急隊を視察したあと、ラオス赤本社を訪れ救急法普及のための資機材の整備状況等を確認しました。2日目から4日目は、ラオス赤が開催する救急法指導者養成講習に参加し、指導者になる予定のラオス赤職員に対して講習内容や指導技術、資機材の取り扱いに関する助言をしました。
 ラオス赤職員に技術指導する柴崎総務課長
ラオス赤職員に技術指導する柴崎総務課長
ラオス赤職員の熱い想い
特に印象に残っていることは?
派遣中、特に印象に残っているのは、ラオス赤職員の救急法普及への意欲とポテンシャルの高さです。現地の救急医療体制の脆弱さを理解しているからこそ、地域住民に救急法を普及することで、ラオスの医療状況を少しでも改善したい、という熱い想いがありました。彼らの熱意が、今後の活動に発展性と持続性を持たせてくれると感じました。現状では、基本的な知識・技術のみ持ち合わせている状況なので、これから応用的な部分を取り入れ、幅をもたせた指導ができるよう次のステップを目指してもらえたらと思います。
 デモンストレーションを熱心な様子で動画におさめるラオス赤職員
デモンストレーションを熱心な様子で動画におさめるラオス赤職員
 無事、指導者に合格したラオス赤職員
無事、指導者に合格したラオス赤職員
今後は、どのような形で救急法普及を行っていくかはもちろんのこと、普及が進むにつれ指導者の養成、資機材の整備、モニタリング等課題は多くあり、この課題を一つずつ適切にクリアしていくためにも日赤として継続した金銭的・人的支援を行うことは必要不可欠です。日赤は、国内での救急法普及のみならず、ラオス赤が救急法を普及できるようこれからも支援を続けていきます。
ひとりでも多くのいのちを、救いたい。
日本赤十字社が実施する国際活動は、NHK海外たすけあいキャンペーンをはじめ、赤十字会員からの会費や寄付を主な財源としています。皆様のあたたかいご支援・ご協力をお願いいたします。