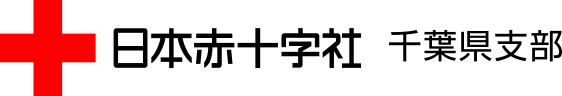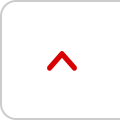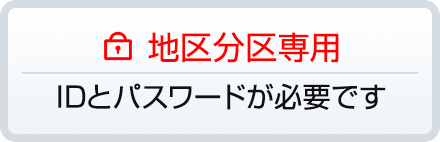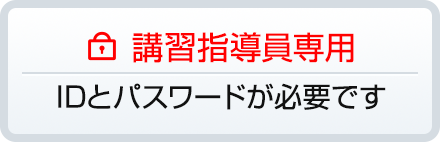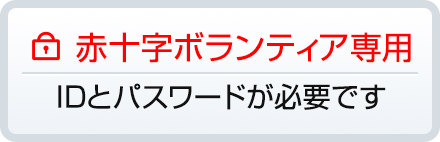中西 加寿也(なかにし かずや)
地球規模の気候変動の影響などで年々大規模災害が増える中、防災意識は高まりつつあります。
今回は20年近く災害救護に携わってきた成田赤十字病院中西加寿也医師に、赤十字が行う災害救護や災害時に生き抜くためのキーポイントについて、お話を伺いました。
多くの災害現場で活動してきた先生ですが、現場によって状況が変わる中、どのような心構えで救護活動にあたっていますか?
「災害救護にベテランはいない」と思っています。地震や台風など災害の種類によって被災状況は異なりますし、地震でも津波があるかないかで全く状況は変わります。そのため、災害現場での活動を多く経験していても、自分が過去に経験したことがそのまま当てはめられる局面はまずありません。ですので、これまで現場で何の経験を積んできたかといえば「答え」ではなく「考え方」の経験です。毎回どの現場でも不安や動揺はつきものですが、何に目を向け何から手をつけるべきかという考え方の筋道は経験として活かせます。
その上で大事にしているポイントは二つあります。一つは、「ニーズは何か?」を考えること。医療が必要なのか、食べるものが必要なのか、着る服が必要なのか、寝る場所が必要なのか。現場をよく把握して必要なものを提供します。
二つ目は、焦らないこと。現場ではあれもこれもとなりがちですが、一気に処理しようとせず、昨日よりも今日、今日よりも明日が少しでも良くなればという心持ちで臨むことが大切だと思っています。

災害救護を行う機関は他にもありますが、赤十字ならではの支援はなんだと思いますか?
災害発生時、医療救護は特に注目されがちですが、被災地において医療のニーズは全体の中の一部であって、医療だけが必要なニーズではありません。どちらかと言えば、衣食住に関わる他のニーズが多くを占めており、医療に限らず被災者が必要とする様々なニーズに応えることができるのが赤十字の強みだと思っています。
また、マンパワーや資材だけでなく、気持ちの面でも安心感を提供できているのかなと感じます。熊本地震の際、赤十字の救護服を着て博多駅周辺を歩いていたら、地元の方に「赤十字の人が来てくれた!ありがとう」と声をかけられたことがあり、嬉しくて今でも印象に残っています。不安な日々を過ごす被災者に赤十字は安心感も与えられると思います。
いくつもの被災地で活動してきた先生から見て、災害を生き抜くために必要だと思われることは何でしょうか?
被災地という過酷な状況下では、人は孤独だと不安になって耐えられません。仲間と一緒にいれば、不安が軽減されます。一人ではくじけてしまいそうな状況でも仲間と一緒なら頑張れる。そのためには、やはり地域でのコミュニティーの形成が不可欠です。新潟県中越地震の際、ある集落では、どの家のどの部屋に避難が困難な住人がいるという情報が共有されていたおかげで、発災後住民たちによる速やかな救助ができました。一方で、都会では隣人でさえどんな人が住んでいるのかわからないことも珍しくなく、公助に頼りすぎてしまう傾向があります。公助はすぐには届かないし、すぐ近くに届くとも限らないので、共助で乗り切る必要があります。特に公助が届かない発災初期には、みなで助け合って、公助が届くまでの時間をかせぎ、公助が届く場所まで移動する必要があります。そのためには、やはり自助だけでなく共助が大切であり、普段から町内会などへ積極的に参加し、共助の体制を培っておくことが重要です。